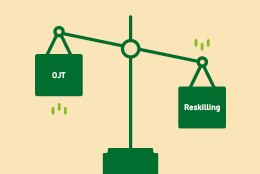HILLTOP株式会社:「人を育てる」使命を追求したら、DXにたどり着いた。稼ぐ仕事は機械に任せ、10年先のビジネスを探す
 HILLTOP株式会社
HILLTOP株式会社
常務取締役 山本勇輝氏
京都府宇治市のアルミ切削加工メーカー、HILLTOPは、製造現場をほぼ自動化し、社員の仕事をプログラミングなどのオフィスワークへと一変させた。自動車メーカーの下請けからオーダーメイド製品の多品種・単品加工に転じ、米国の娯楽産業など世界の錚々たる企業・組織と取引する同社が「最大の使命」に掲げるのは、利益追求でも技術革新でもなく「人を育てる」こと。常務取締役山本勇輝氏に、「油まみれの3K仕事だった」という現場作業からプログラミング、さらに近年のAI導入に至る仕事の変化のなか、どのように人材を育ててきたのかを聞いた。
自動化で納期短縮、社員の反復作業も回避
――工場の自動化、AIの導入と、時代に応じて新しい技術を導入してきました。
「削ってなんぼ」の仕事に「本当に人がやるべき仕事なのか?」という疑問を抱いたのが、変化のきっかけでした。ルーティーン化した切削加工の作業を機械で自動化し、社員にはもっとステップアップした知的作業をやってもらいたいと考えました。
そこで、職人によって異なっていた勘と経験を集めて分析し、当社の標準的なやり方として確立した上でデータ化し、誰もが安定した品質の製品を製造できる「ヒルトップ・システム」という生産管理システムを稼働させました。社員の仕事は日中、デスクに向かってプログラミングをすることに変わり、人がいない夜間でも機械が製造するようになりました。一度手掛けた製品の製造プロセスはデータ化するため、再発注があれば自動で作れます。このため社員は常に新しいものづくりに挑戦し、スキルアップや刺激を得られるようになりました。
――工場勤務からプログラマーへ、社員に求められるスキルも変わったと思います。どのように人材を育成していますか。
 新卒で入った社員も、半年で戦力化できる教育システムを構築しています。詳細なマニュアルを作り、「なぜこの作業が必要か」「なぜこの数値を採用するのか」を論理的に教えるとともに、実際にアルミを削らせて、理論と実践の両方から、ものづくりの根幹となるスキルを学んでもらいます。入社後半年ですべての部署を体験します。
新卒で入った社員も、半年で戦力化できる教育システムを構築しています。詳細なマニュアルを作り、「なぜこの作業が必要か」「なぜこの数値を採用するのか」を論理的に教えるとともに、実際にアルミを削らせて、理論と実践の両方から、ものづくりの根幹となるスキルを学んでもらいます。入社後半年ですべての部署を体験します。
そして、プログラミングも半年で組めるようになります。「ヒルトップ・システム」を使えば、どの部位にどの刃物を使うか画面上でクリックすることで最適な加工方法が自動的に選択されます。このため専門知識を持たない者も、ゲームをクリアする感覚で、プログラムを組めるのです。
――社員のローテーションを頻繁に行っているのはなぜでしょうか。
さまざまな職場を経験してもらうことで、企業としての生産性は下がるかもしれません。しかし社員が定期的に新しい仕事を学ぶことで、マンネリ化やモチベーションの低下を防ぐだけでなく、スキルの「引き出し」が増えることが期待できます。
例えば営業担当であっても、製造現場を理解していれば、クライアントに的確なソリューションを提案できます。逆に製造現場の社員も営業の経験があるので、顧客ニーズを想像しながらものづくりに取り組めます。SEも製造現場が出す要望の背景を理解し、システムを作りこむことができるなど、互いの仕事を理解していることのメリットが大きいのです。
実践での試行錯誤が、力をつける近道
――人を育てる上で、どのようなことを大事にしていますか。
実務に即した形で勉強をさせることを大切にしています。何といっても、納期が迫るなか、必死に試行錯誤を繰り返すことが、社員が短期間で力をつける最も有効な方法です。ただ、この時必要なスキルは事前に学んでおく必要があるので、何を学ぶべきかを明確化した上で、外部と連携するなどして教育カリキュラムを構築することに力を入れています。
将来ニーズが高まるだろうと思ったら、現在のわれわれの手には余るような仕事を引き受けるのも、技術習得の1つの方法です。当社のスキルでは足りず、別の会社に足りない部分を請け負ってもらうことになって全然もうけが出ないこともあります。それでも、社員は外注先での手伝いなどを通じて少しずつ、新たな技術を学んできてくれます。
――仕事が変わるなかで、職場に新たな課題は起きていますか。
海外に進出して受注が伸びると、新たな問題が生じました。プログラマーの業務量が増え、人手が足りなくなったのです。また、作業の最適化、自動化を突き詰めた結果、作業が単純化し、社員が創造力を発揮する余地が狭くなりました。ルーティーンワークから人を解放するという信念のもとに自動化を追求してきたにもかかわらず、それを追求するとプログラミングもルーティーン化し、社員が仕事に飽きてモチベーションが下がる、というジレンマが生じました。
――解決策はありますか。
「次の一手」として、AIの活用や新しいビジネスモデルづくり、新事業に必要な技術の開発、デザインのようなクリエイティブな分野、人にしかできない研究などに取り組んでもらっています。極端に言えば、目先の利益を稼ぐ仕事は、AIやロボットに任せればいいのです。
企業の業務のうち、コア技術に関わるのは全体の20%で、それ以外は誰にでもできる「作業」だと言われます。本来は80%を機械に担わせ、人間は20%をより研ぎ澄ますことにエネルギーを費やすべきです。
――新しい取り組みには、どのようなものがありますか。
2019年に新設した企画開発推進部のメンバーが中心となって、ルーティーンになりかねないプログラミングをAIで自動化する「COMlogiQ」を開発しました。加工する製品の3次元(3D)データをクラウド上にアップロードすると自動的に加工プログラムを生成するシステムで、自社で使用するだけでなく、2022年1月にサービスとして提供することを予定しています。24時間稼働できて、プログラミングに要する時間も3分の1に短縮されるので、熟練技術者約30人分の作業をこなせます。
中小企業の多くが、アイデアはあってもプログラマーがいないので形にできない、という悩みを抱えているので、われわれの技術をオープンにすることで、彼らの役に立てないか、と考えたのです。
味覚やデザイン、感性を活かす。「人の手で削る」ものづくり追求も必要
――それ以外にも追求されていることはありますか。
プロダクトデザインを含めて、AIでは自動化できないハイエンドゾーン、20%のコア技術をものづくり屋として研究しようと思っています。同時に、機械では再現できず、人の手で削り出すしかない技術も追求するつもりです。カスタマイゼーションが進み、個人のニーズに合わせて固有にデザインされた製品が求められるなか、陶芸のように人間の感性によって生み出すものづくりを、あらためて学び直すことも大事だからです。
――そのような仕事をどのように学ばせているのでしょうか。
顧客から言われたとおりのものを作るだけでなく、その先にいる消費者の感性を想像し、彼らが求めるものは何かを考えながらものづくりをする機会を設けています。
例えば以前、京都にある老舗の和菓子屋さんと、お菓子の「もなか」の型を作りました。「もなか」は型につけた切れ込みの大きさによって、焼き上がりがもっちりしたりパリッとしたりと、食感が変わります。そして対価を頂く代わりに、社員をテストに立ち会わせてもらったのです。自分たちの作った型が、実際にどんな製品を生み出すのかを、見る機会はなかなかありません。和菓子屋さんとともに、この店ならではの「味」を作る経験は、社員にとって非常に有意義な学びになりました。
社員を単純作業から解放し、成長できる職場を作る
――自動化とAI導入で、会社をどのように変えたいと思ったのでしょう。
 「自分がやるのは嫌だ」「自分なら飽きるな」と思った仕事をなくしたい、と思ったことにつきます。「DXを進めたい」という思いはなく、社員に楽しく働き、力を伸ばしてもらうための手段として、自動化やAIを選んだだけです。「自分が嫌なことは、人にもしてはいけません」って、親に教えられましたし(笑)、会社は僕一人では成り立ちませんから。
「自分がやるのは嫌だ」「自分なら飽きるな」と思った仕事をなくしたい、と思ったことにつきます。「DXを進めたい」という思いはなく、社員に楽しく働き、力を伸ばしてもらうための手段として、自動化やAIを選んだだけです。「自分が嫌なことは、人にもしてはいけません」って、親に教えられましたし(笑)、会社は僕一人では成り立ちませんから。
講演などでよく「どうすればAIを活用できるのですか」と聞かれますが、こちらが「何の課題を解決したいんですか」と聞き返すと「AIを使って何かしたい」と言われるだけで、目的と手段が逆転していると感じます。イノベーションの大半は、問題解決の手段の1つでしかないと思います。
――自動化やAI活用の目的が利益拡大や企業成長ではなく、「人を育てること」なのはなぜですか。
社員のスキルや意欲を高めるためのコストを削ぎ落とせば、短期的な利益は上がるかもしれません。しかし社員をルーティーンから解放し、5年先、10年先のビジネスを作る仕事へシフトさせるのが経営者のなすべきことだし、それができない企業は、中長期的には先細りしていくのではないでしょうか。
自分が獲得したスキルやノウハウを標準化・データ化して他人へと移してしまえば、その分自分のなかにキャパシティができ、新しいスキルや経験を取り込むことができます。
社員の離職を恐れ、社外で通用するスキルを習得させたがらない経営者もいると聞きます。しかし人に投資する経営者に、賃金以上の魅力を感じてくれる社員もいると思います。
聞き手:石川ルチア・石原直子
執筆:有馬知子


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ