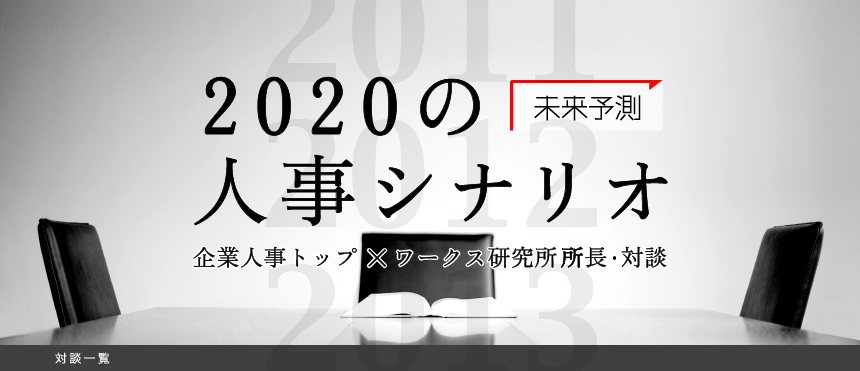
Vol.14 中島 与志明氏 アステラス製薬

アメリカが重要な戦略基点に
大久保 御社は、長期経営ビジョン「VISION 2015」を2006年に発表しています。それに関連して、まずは今後の人事課題を教えてください。
中島 弊社は、2005年4月に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併して誕生しました。合併の目的は規模を確保し、ますます激化するグローバル競争で「勝ち上がる」ことでした。2007年あたりから、そのための積極的な投資を始めました。そして今、2015年、2020年を考えた場合、最大の人事課題はグローバル化とダイバーシティ(多様性)です。
大久保 「VISION 2015」を拝見すると、グローバル・カテゴリー・リーダー(GCL)を目指す、とあります。
中島 薬というのは巨大な市場が1つあるというわけではなくて、糖尿病を治す薬とか、高血圧に効く薬とか、小さな市場をいくつも寄せ集めたものなのです。GCLというのは、専門医の処方が中心となるいくつかの市場(カテゴリー)において、付加価値の高い製品をグローバルに提供することで業界のリーダーを目指す、というビジネスモデルです。具体的には、従来から強い泌尿器、移植という2領域に加え、ガン領域においてもGCLを目指していきます。そのガン研究の最先端の地であり、規模的にも世界一となっているのがアメリカの医薬品市場です。そして、そこで医薬品の承認を司っているFDA(アメリカ食品医薬品局)は、各国の新薬の承認や薬事行政に強い影響力を持っています。グローバルにビジネスを展開しようとする場合、アメリカに医薬品の開発拠点を置くことのメリットは小さくはありません。当然、数多くの優秀なリーダーたちもアメリカに集まります。合併前のように、販売以外のすべてを日本で行うというわけにはいかず、市場に最も近い最適地に、国籍を問わず、優秀な人材を集めなければなりません。ダイバーシティが重要になるゆえんです。
大久保 そうしたグローバル化の進展は、薬品領域によって濃淡があるのでしょうか。
中島 基本的にありません。自動車や食品メーカーだったら、国ごとの商品開発が必要ですが、製薬は違います。サイエンスという共通言語で語られる部分が非常に大きいので、医療制度やパテント(特許)の仕組み、民族による医薬品の効果の現れ方の違いという国の事情による影響はあるものの、ほかの消費財よりグローバル展開がずっと容易です。日本の自動車会社だったら、独自の品質を担保する仕組みとして、5年、10年かけて現地人材を育成しますが、我々がそれをやったら競争に負けます。最前線の最高の情報や知識を集めて、すばやく製品や戦略に変えていくというやり方でないと。幅広い視野を持ち、グローバルで意思決定ができるリーダーを育てなければならないのです。
大久保 人材育成はどのように行っているのですか。
中島 日・米・欧の3カ所で、グローバルリーダーを育てる選抜型の研修を行っています。各拠点の部長級27人が日本に集められ、2011年10月にキックオフしました。GCLをいかに推進するか、2020年に向かってはどんなビジョンが必要か、といったことを、互いに切磋琢磨しながら考えてもらうわけです。今従業員が1万6000人ほどいて、そうした次世代リーダー候補が70人から100人います。27人の次は20人、その次も20人とやっていくと、同じ研修で結ばれた濃密なネットワークが生まれます。そのくらいの数ですとトップからも目が届きますが、規模が大きくなるとそうはいきません。この規模ならではの勝ち方を追求して、存在感のある企業になりたいですね。
大久保 最近よく聞くのですが、外国人と日本人が交ざって研修を受けると、日本人が大人しく、外国人のほうがリーダーシップを発揮する傾向が強いそうです。御社ではいかがでしょう。
中島 使う言葉が英語ですから、やはり英語が母国語の外国人に有利なことは否めません。ただ、抽象度の高い議論になった際、ある日本人が議論を中断し、メンバーに同時通訳の機械をつけてもらってから自分の考えを述べたところ、外国人を含め、みんな感心して聞き入っていた、というエピソードがありました。ですから、少々シャイであったり、英語が下手であったりしても、最後はやはり卓越した専門性や思考力を持つ人が一目置かれるということではないでしょうか。

1人の採用にエネルギーをかける
大久保 グローバルやダイバーシティというのは、かなり達成されたとお考えですか。
中島 正直、まだ道半ばですよ。というより、ビジネスのほうが半歩先を行ってしまい、人事はそれに遅れているといったほうがいいかもしれません。
大久保 ガン領域に力を入れているということですが、人の採用はうまくいっていますか。
中島 採用はアメリカの人事が担当していますが、欠員がなかなか埋まらないようです。それだけ、人材要件が厳しく、また獲得競争が激しいということでしょう。
大久保 GCLという戦略自体が、その分野の専門人材を惹きつける材料になりますが、加えて研究者に他社より魅力的な仕事環境を用意してそれを打ち出す必要があるでしょうね。
中島 そうですね。大きな課題です。また、日本と違うのは、人材の流動性が高いこと。特に1人の優秀な人材が移ると、自分も移ってその人の下で働きたいという人が多い。アメリカの大統領とそのスタッフの関係と同じですね。最近、ある製薬会社から来てくれたアメリカ人は内科学会の重鎮でもあり、優秀な元部下を何人か引き連れてきました。
大久保 自分の知り合いを連れてくるネットワーク採用は日本ではあまり行われていませんが、ほかの国では常識です。採用が成立した時点でお金を払う企業もありますが、日本の場合、それをやると職業安定法に抵触してしまうのです。これは日本企業全般にいえることですが、中途で人を採用することがあまりうまくありません。裏返していえば、新卒一括がやはり採用の王道ということです。
中島 その点、1人採用するのに大変なエネルギーと時間をかける欧米のやり方を我々も見習わないといけません。
リーダー・フォロワーの関係開発を
大久保 今までお聞きした、採用と育成以外の課題に関してはいかがでしょう。
中島 横軸に個人と組織、縦軸に管理と開発と置く4象限を考えた場合、1990年代の終わりから、個人・管理に関する施策が目白押しだった半面、組織・開発に関する施策がなおざりにされてきたと思います。成果主義しかり、360度評価しかり、コンピテンシーしかり。手遅れにならないうちに、ここを何とかしなければ。逆に、アメリカ企業は1980年代から組織開発に非常に力を入れてきています。個人主義の国だから、チームで成果を出すということに意識的に取り組んでいるようです。
大久保 組織開発は日本企業のお家芸であり、人事があえてやらなくても、という慢心があったのかもしれません。
中島 そうでしょうね。たとえば360度評価をやって部下からの評価が悪くて悩むマネジャーがいたとしても、その悩みを聞いて助言してくれる駆け込み寺の機能が今の人事にはないのです。
大久保 「チームで成果が出せない」のは、部下にも問題があるのではないでしょうか。つまり、リーダーに対して健全なフォロワーシップをとれる部下が少なくなっている。フォロワーには、リーダーのことを理解共感し、しかるべき貢献を行うこと、困難に直面したリーダーに対して建設的な提案や、場合によっては批判も行うこと、この2つの役割が必要です。
中島 幸いなことに、この人のあとについていけば大きな成果につながるはずだ、という上司に私は恵まれてきました。組織開発のなかでも、まさにリーダー・フォロワーの関係開発が重要だということでしょう。
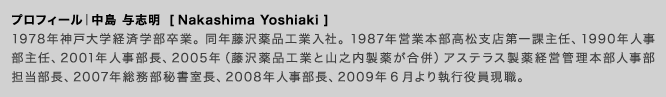
(TEXT/荻野 進介 PHOTO/平山 諭)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ