頂点からの視座石井幹子氏(照明デザイナー)
光の美しさを伝える信念が
壁を乗り越える原動力に

沖縄万博、東京タワー、レインボーブリッジ、白川郷合掌集落などの照明デザインを手がけてきた石井幹子氏は、この業界で押しも押されもせぬ第一人者だ。同時に、照明デザインという概念を知る日本人がほとんどいなかった頃から活躍してきた先駆者でもある。
さまざまな案件で周囲を巻き込むパワーはどこから生まれるのか。そして、今もなお新たな試みに挑戦する原動力は何なのだろうか。
 IshiiMotoko_1938年生まれ。東京芸術大学卒業後、フィンランドとドイツの照明設計事務所で経験を積んだ後に帰国。1968年、石井幹子テザイン事務所を設立。国内外でさまざまな景観照明や光に関連したイベントなどを手がけてきた、照明デザイン界のパイオニア。2000年、紫綬褒章を受章。
IshiiMotoko_1938年生まれ。東京芸術大学卒業後、フィンランドとドイツの照明設計事務所で経験を積んだ後に帰国。1968年、石井幹子テザイン事務所を設立。国内外でさまざまな景観照明や光に関連したイベントなどを手がけてきた、照明デザイン界のパイオニア。2000年、紫綬褒章を受章。
― 照明デザインの仕事を飴めたきっかけをお教え下さい。
高校生のとき、国立近代美術館で「グロピウスとバウハウス」と題された展覧会を見て、工業デザインという仕事の存在を知りました。小さい頃から絵を描くことが好き。また、発明家に憧れていた私にとって、工業デザインこそ天職だと直感したのです。そこで東京芸術大学でデザインを学び、卒業後はデザイン事務所に就職しました。当時はデザインの勃興期で経験者が少なかったため、大学を出たばかりの私にもさまざまな仕事に携わる機会を与えていただきました。
そんななか、私は照明器具のデザインを担当しました。試作品に電気を通したときの衝撃が、照明デザインの道に進む決め手でしたね。光が、周囲のモノの形を美しく照らし出すのを見て、なんて素晴らしいんだろうと感動したのです。それで、もっと照明について学びたいと決意しました。
― その後、フィンランドに渡られたのですね?
当時は北欧のデザインが世界中で注目されており、北欧製の照明器具が日本でもしばしば紹介されていました。それらを見て、北欧で照明デザインを学ぼうと決心したのです。ただ、北欧で勉強できる奨学金は皆無。当時は外貨の持ち出しが500ドルまでに制限されていたので、北欧で学ぶには、現地で働くしかありませんでした。そこで私は、海外のデザイン誌に掲載されていたフィンランドの照明器具デザイナーに、手製の作品集と手紙を送りました。それが認められ、ヘルシンキの照明設計事務所で働くようになったのです。
― 当時、海外で働くことは相当ハードルが高かったはずです。迷いはありませんでしたか?
いいえ。私はいつも、「ものごとには、何か解決策がある」と考えています。たとえば、フィンランドで経験を積んでドイツの会社にスカウトされたとき、私はドイツ語がまったく話せない状況でした。でも、言葉がダメなら、人の倍の速さで仕事をすればいいと思ったのです。へこたれて諦めるのではなく、何とか前に進む方法を工夫する。それが、私のやり方です。
思いどおりの照明を実現するため周囲を説得
― 帰国後は、さまざまな場所で照明デザインを手がけてこられました。仕事をされるなかで苦労されたのはどんなことでしょうか?
厳しい条件下で照明をデザインするときは、知恵を絞ります。たとえば、白壁づくりの建物が立ち並ぶ倉敷市の「美観地区」の案件は大変でした。倉敷は観光地なので、電気工事のために道を掘り起こしたり、堀の水を抜いたりするのは不可。また、昼間の景観に影響を与えないよう、新たな照明器具の設置もできませんでした。そこで私は、既存の街路灯を改造したり、消費電力の少ないLED(発光ダイオード)の投光器を追加するなどして、条件内でのライトアップを実現したのです。また、街並みに生活感を出すため、空き家の持ち主を一軒一軒回って室内に行灯型の照明を置いてもらう交渉もしました。
― 石井さんが自ら、説得に当たられたのですか?
はい。「電気代は市から補助される」「照明が倒れても、火事にはならない」「照明を入れれば、街並み全体が美しく変わる」と説得すれば、ほとんどの人はわかってくれました。楽しかったですよ。
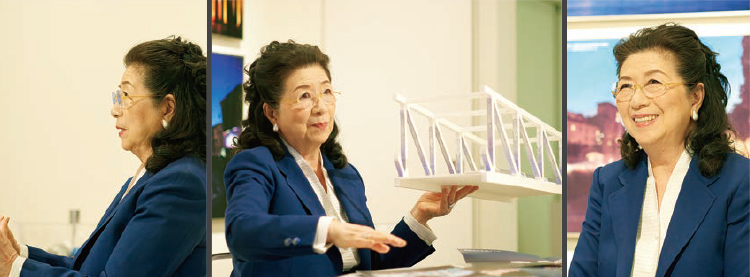
100年先を見すえたデザインを模索する
― 時には、照明デザインに理解のない人から反対され、悩まれたこともあると思います。それを乗り越えた原動力とは?
光は美しい。そして、実際に見てもらえれば、よさを必ずわかってもらえるという信念でしょうか。
東京ゲートブリッジを手がけたときは、近くを通る船の関係者から「照明がまぶしくて航行の邪魔になるのではないか」と反対されました。でも、この橋の寿命は100年以上。設計当時は東京オリンピック・パラリンピックの招致は決まっていませんでしたが、いつかオリンピックのような大イベントが実現して埋め立て地に競技場が作られたとき、そこから見た橋の照明がみすぼらしかったら絶対に悔いが残ると思いました。そこで、特定の海域に船が入ると光が弱くなる仕組みを工夫。さらに、橋があらかた完成した段階で照明を仮付けし、光がどのように見えるかテストしました。救命胴衣を着けて小さな船の手すりにしがみつきながらの確認作業でしたが、これも決して辛くはありませんでしたよ。思いを実現しようと思うと、前向きな工ネルギーが生まれてくるんです。
そうして光をつけてみると、ほとんどの人が喜んでくれました。反対していた人も「私だって心のなかでは賛成していたんですよ」と笑ってくれたのです。そのときは、まさに大満足でした(笑)。
― 石井さんは、今でも新しい挑戦をされているそうですね。
ええ。パリで毎年行われている展示会には、娘(照明デザイナーの石井リーサ明理氏)と共に参加。今年は、日本の伝統工芸品である絹織物を使ったオブジェを出展予定です。「和+最新の光の技法」という組み合わせがどんな効果を発揮するか、楽しみですね。また別のプロジェクトでは、色のパレットを操作すると、それに合わせて部屋全体が色に染まるような展示を構想中です。こちらは、リアルタイムで光が変化するという、私にとっても未経験な分野です。
照明デザインの仕事を始めてから、もう50年ほど。でも、今もなお、仕事はワクワクしますね。私にとって、新しいことに挑戦することは楽しくて仕方がないんです。
Text=白谷輝英 Photo=橋本裕貴
After Interview
- 自分が「いい』と思ったものには、決して妥協しない。インタビューを通じて、石井さんから一貫して伝わってきたのは、そんな強い意志だ。この意志の強さはどこからくるのだろうかと考え、インタビューを進めた。
石井さんが自分の事務所を構えたのは1968年。当時の日本では、照明デザインという考え方自体を理解してもらえず、相当苦労したという。しかし、そこで諦めることなく、出版社などを訪問し、自分のアイデアを、ぶつけ続け、時代の寵児であった著名な建築家たちを訪問するというチャンスを自ら創り出した。そして、彼らとの議論を通じて、大阪万博におけるライトアップという大きな仕事を掴み取る。これをきっかけにして沖縄海洋博、東京タワー、レインボーブリッジなどに活躍の場を広げていく。
その決して諦めない姿勢を生み出す原動力は何なのかを問うてみると、極めてシンプルな答えが返ってきた。「だって、照明の光って本当に美しいものだから。その美しさを、できるだけ多くの人に見てもらいたいだけなんですよ」。そう語る石井さんの、純粋な目の輝きが、今も忘れられない。
我々は、石井さんと同じくらいの純粋な志を持って日々の仕事に向き合えているだろうか。そう問いかけられたような気がした。
聞き手=清瀬一善(本誌編集長)
