生き物のチカラに学べ「死んだふり」に学ぶ私たちの生存戦略
外敵に襲われると、「死んだふり」をする生き物がいる。しかも、死んだふりは、それほどめずらしい行動ではないらしい。「昆虫から魚、力エルなどの両生類、鳥類、捕乳類まで、さまざまな生物で観察されています。ほとんどの動物に見られる行動と言ってもよいでしょう」こう語るのは、進化生物学者の宮竹貴久氏。世界で初めて死んだふりが生存に有効であることを実験によって立証した、死んだふり研究の第一人者だ。たとえばニワトリは夜、野犬に捕まると、ダラッと力を抜いて死んだふりをする。噛みついた野犬は一瞬驚いて、ニワトリを離してしまう。その隙にニワトリがスタスタと逃げていったという光景は、昔から観察されているという。なかでも有名なのは、オポッサムというネズミに似た動物だ。犬などに出くわすと、ばったりと倒れて動かなくなる。ぽかんと口を開けて横たわる姿は、本当に死んでいるかのような名演技ぶりだ。
動かないことで「エサ」ではなくなる
死んだふりとは、動かずにその場をやり過ごす戦略だ。単純といえばこれほど単純な作戦はない。一般的に考えれば、食うか食われるかの厳しい生存競争の下では、逃げ足の速いほうが生き延びる確率は高いのではないかと思える。動かないという選択が、なぜ有利に働くのか。「実は、動きに反応する捕食者に対しては、死んだふりはとても有効な戦略なのです」ハエトリグモを例にとれば、飛び回るハエを一瞬で仕留めて決して離さない。しかし噛みついた瞬間、死んだふりをする甲虫については、まずはその固さに驚いていったん離してしまう。しばらくじっと観察して、甲虫がまったく動かないことを確認すると、興味を失ってしまうのだという。ある種のカエルや力マキリなど、動くもの=エサと認識している生き物は少なからずいる。エサを獲ることは生き物にとって生死を分ける重要な行動なので、死んでいるかもしれない動かないものは無視して、確実に生きている動くものに特化し、それを捕らえる能力を発達させたほうが効率がよいからだ。そうした捕食者の関心から逃れるのに、死んだふりは極めて有効な方法といえる。
 死んだふりで有名なのがオボッサム(フクロネズミ)。英語で「play opossum」といえば、「死んだふりをする、とぼける、タヌキ寝入りする」という意味で使われる。
死んだふりで有名なのがオボッサム(フクロネズミ)。英語で「play opossum」といえば、「死んだふりをする、とぼける、タヌキ寝入りする」という意味で使われる。
動き回る仲間の後ろで身を潜めてやり過ごす
「さらにもうひとっ、集団のなかで死んだふりをすると、周囲で動き回っているほかの個体に捕食者の注意をそらすことができるという効果もあります」いわば仲間を犠牲にして自分だけ生き延びようというのだから、ずいぶん残酷な話だ。人間社会のなかでは、目立つ者の陰でじっと身を潜めて何事もやり過ごしているタイプの人は、間違いなく嫌われるだろう。思わず「ずるい」と言いたくなるが、もちろん生物にそんな意図はない。
実は死んだふりをする虫は、死んだふりをしない虫と比べて、脳内のドーパミンの量が少なく、もともとあまり活動的でないことがわかっている。動かないでやり過ごすというのは、アクティブに動けないタイプの虫の「弱者の戦略」といえるかもしれない。「以前、長いこと死んだふりをしている虫が、エサと間違われてアリに運ばれているところを見たことがあります(笑)。同じ集団のなかにも、いろいろな個性を持つ個体がいて、その場面、場面によって有利になったり、不利になったりする。結果的に、死んだふりをする個体も、動き回る個体も一定の割合で生き残っているということです」
生き延びる強さと協調する知恵と
生き物は「誰かを犠牲にしよう」とも「皆で協力しよう」とも考えてはいない。環境に適応して変化してきた結果、現在のバランスに落ちついたということだ。
同じように進化してきたはずなのに、なぜか人間だけは、モラルや感情を持ち合わせている。妬みや憎しみにとらわれることもあれば、自分のことだけではなく皆の幸せに思いを馳せることもある。
人問も生き物である以上、自分自身がたくましく生き延びていくことがすべての基本である。しかし、モラルや感情を持っ人間は、食うか食われるかの二者択一ではなく、仲間や組織や社会の利益を損なうことなく、自分の利益を追求していく道を選ぶべきではないか。その二律背反に折り合いをつけていくことこそが、人間の知恵といえる。
「モラルや感情を持たない生物の世界にも『共生』という関係があります。二者がお互いにメリットを与え合う協調的な生き方のことです」私たちはこの先、人間らしい共生関係をいかに築いていくことができるのか。今こそ、生き物のチカラに学ぶときだ。
Text=瀬戸友子 Photo=笹木淳 Illustration=寺嶋智教
-
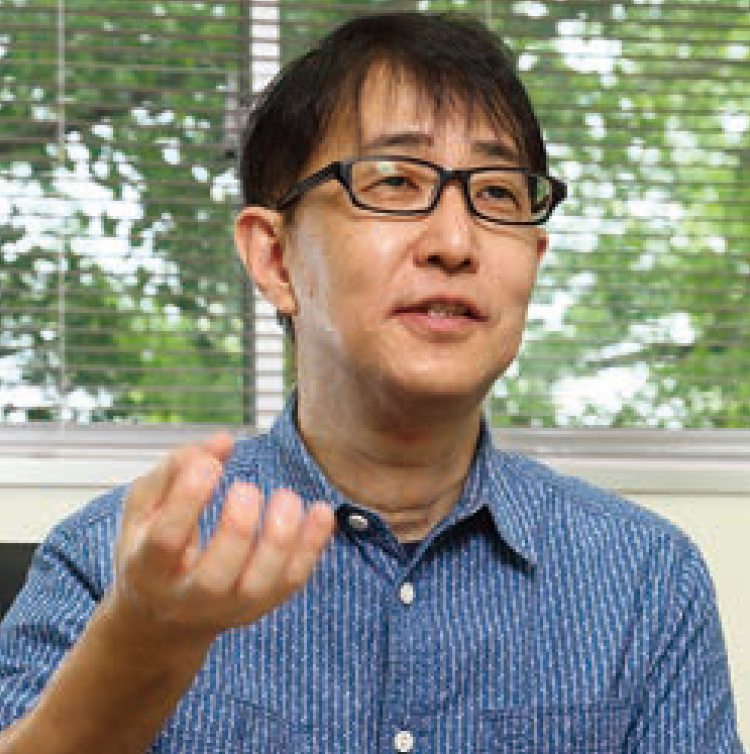 宮竹貴久氏
宮竹貴久氏 - 岡山大学大学院環境生命科学研究科教授。
- Miyatake Takahisa 琉球大学大学院農学研究科修了後、沖縄県職員として10年以上慟く。九州大学大学院理学研究院で理学博士を取得後、ロンドン大学生物学部客員研究員を経て、2008年より現職。著書に『「先送り」は生物学的に正しい』(講談社+a新書)など。
